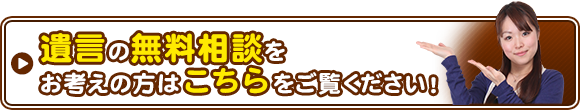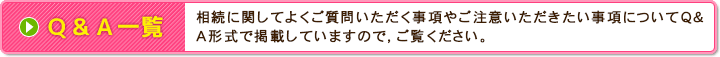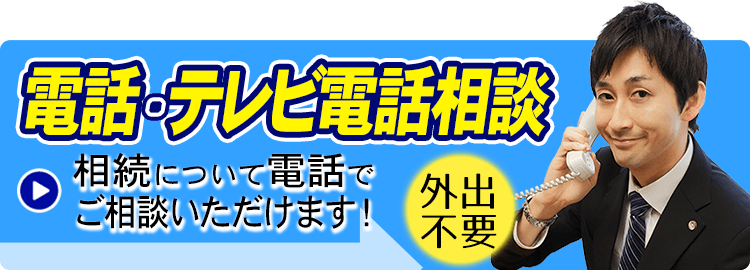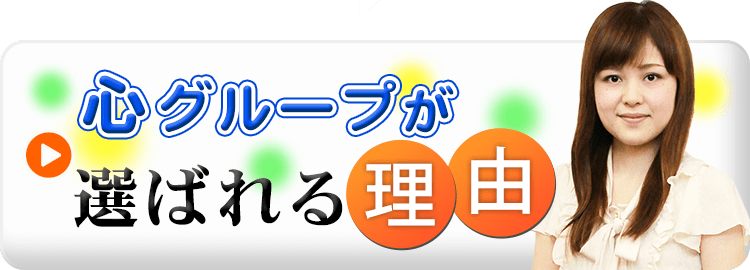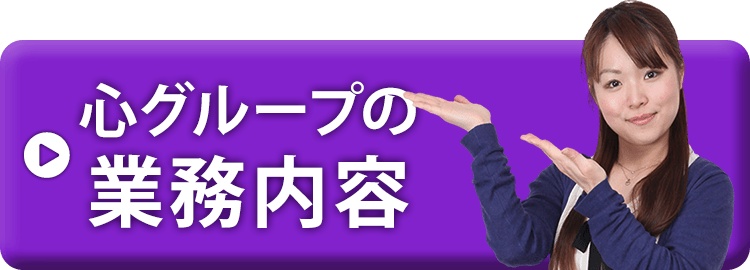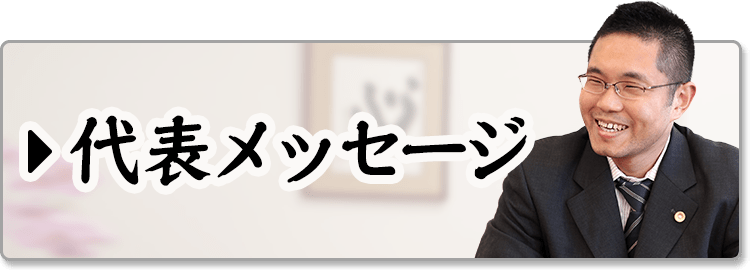公正証書遺言を作成する場合の流れ
1 公正証書遺言は公証人によって作成される遺言
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、実務において作成されるものの多くは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言としての法的な効力は、基本的にどちらも同じですが、作り方や、作るための負担の大きさ、無効になるリスクという点で異なります。
公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が文章を作成するので、通常であれば形式的な不備が発生することはありませんし、公証人が遺言者の面前で遺言の内容を確認してから確定しますので、遺言能力や偽造の疑いも生じにくいという特徴があります。
以下、公正証書遺言作成の具体的な流れについて、説明します。
2 財産の調査と整理
公正証書遺言に限ったことではありませんが、遺言を作成する際には、まず遺言者の方の預貯金や不動産、有価証券など、どのような財産をどれだけ保有しているかを正確に調査します。
公正証書遺言の作成の際には、公証人の手数料算定のために、遺言に記載する財産の評価額が必要になりますので、預貯金通帳、不動産登記事項証明書・固定資産評価証明、有価証券残高が記載された書面など、客観的な資料も用意します。
そのうえで、どの財産を、誰に相続または遺贈するかを検討していきます。
なお、遺言に記載しなかった財産については、通常の遺産分割協議の対象となりますので、遺言に記載する財産に抜け漏れがないようにすることが大切です。
3 遺言の下書き・公証役場との調整
財産の調査と、誰にどの財産を取得させるかの検討をしたら、公正証書遺言の下書きをします。
並行して公証役場に連絡をし、公正証書遺言を作成したい旨を伝えます。
その後、公証役場に遺言の下書きを提出し、内容を確認してもらい、問題のある部分の指摘があった場合には訂正します。
遺言に記載する文言が固まり、手数料等の見積もりもしてもらったら、公証役場等で公正証書遺言を作成する日時を調整します。