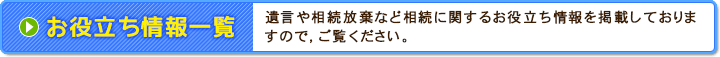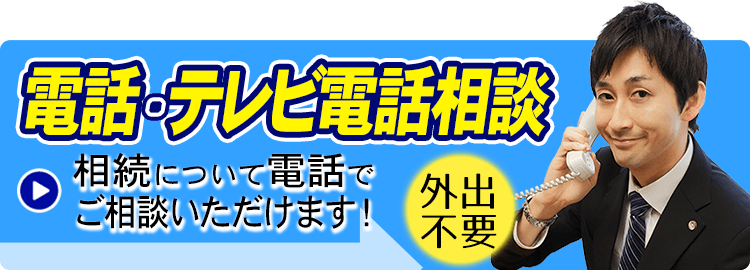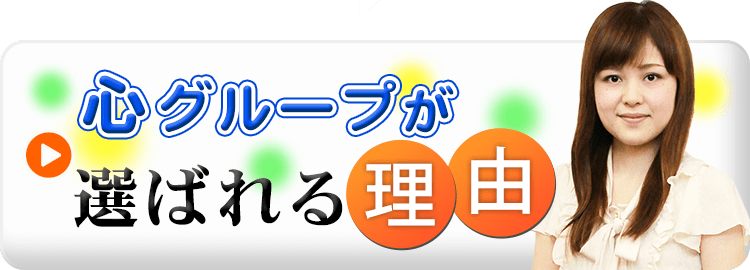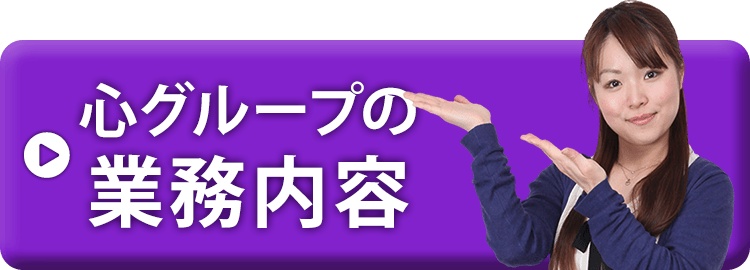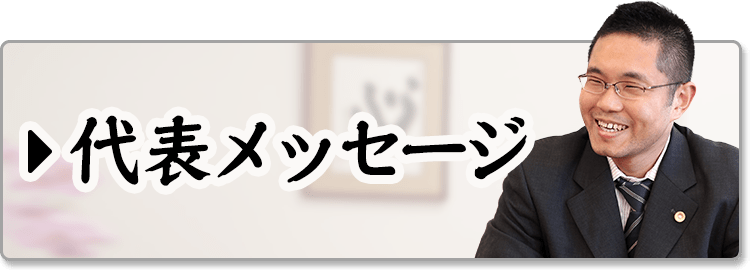遺産分割協議書の作成に関するQ&A
遺産分割協議書はどのような流れで作成するのですか?
相続開始後、まず相続財産や相続人を調査します。
相続財産や相続人を特定したら、どの財産をどのように分けるかについて、相続人同士で話し合いを行います。
話し合いの結果、財産の分け方が決まれば、決まった内容を明確に残しておくため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書はどのように作成するのですか?
遺産分割協議書の様式は決まっておらず、パソコンでも手書きでもかまいません。
遺産分割協議書の内容としては、被相続人が誰であるか、死亡日や最後の住所、本籍地などの情報のほか、相続人が誰であるか、具体的にどの財産を誰が取得するのかを記載することが一般的です。
日付を記入し、相続人全員が署名し、実印で押印します。
遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成し(たとえば相続人が3名なら3通)、各自1通ずつ保有することが多いです。
作成の方法としては、相続人全員が集まって遺産分割協議書に署名押印することが多いですが、書面を郵送して順次署名押印することも可能です。
遺産分割協議書に署名押印してもらえない場合はどうしたらよいですか?
遺産分割協議書を作成したものの、相続人全員の署名押印が得られない場合、最終的には遺産分割調停や審判といった手続きで財産の分け方を決めることになります。
遺産分割協議書の作成後に、協議のやり直しはできますか?
遺産分割協議書の作成後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことは、原則としてはできません。
しかし、遺産分割協議が成立した後でも相続人全員が同意している場合には可能です。
その場合、やり直しによって税金や登記などの負担が大きくなることがあるため注意が必要です。
また、相続人の一部が欠けていた場合は遺産分割協議が無効となるので、やり直しが必要となります。
そのほか、詐欺や脅迫があった場合などでも、合意を取り消したうえで、遺産分割協議をやり直しとなることがあります。
遺産分割調停の流れについてのQ&A 相続税の課税対象財産に関するQ&A