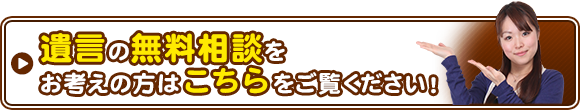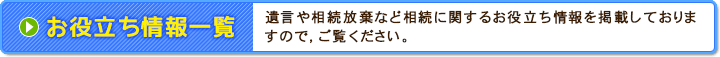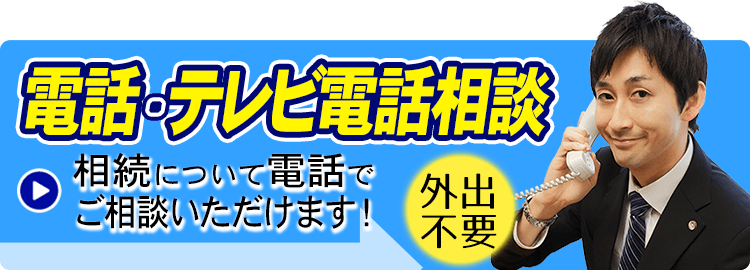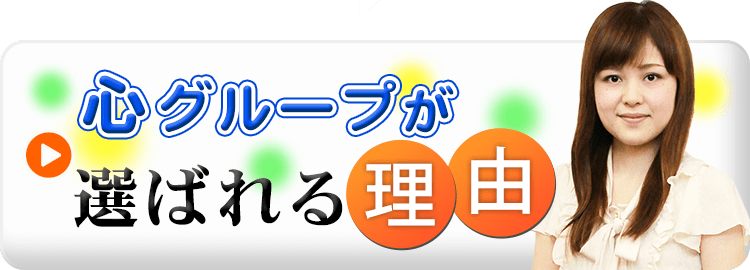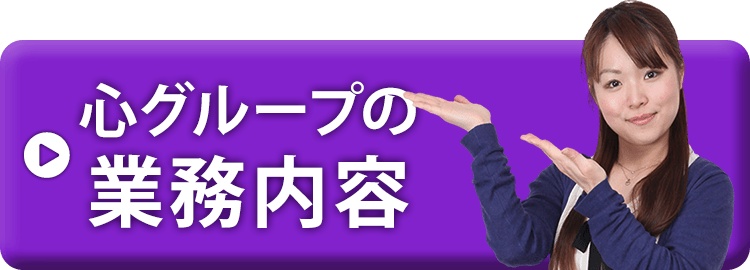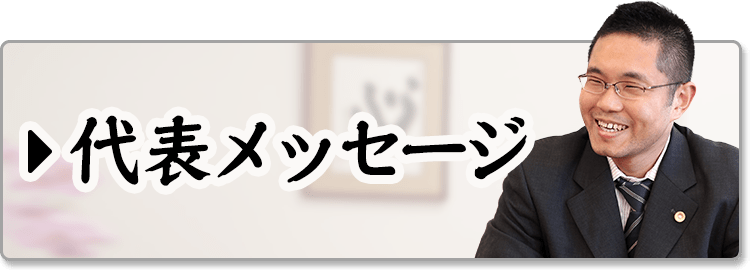自筆証書遺言を書く上での注意点に関するQ&A
自筆証書遺言を作成する場合に必ず記載しなければならないことは何ですか?
自筆証書遺言は、遺言の内容、日付、氏名の記載と、押印が必要です。
これらのうち一つでも欠けると、原則として遺言は無効になります。
また、財産目録を除き、遺言の内容、日付、氏名は全て自署することが必要です。
もしパソコンで作成したり、誰かに代筆してもらったりした場合、遺言は無効になります。
遺言の内容はどんなことに注意が必要ですか?
遺言の内容は自由ですが、法律で決められた範囲にしか効力がありません。
法律で記載が認められていないことを遺言に記載しても、法的な効力が発生しませんので、遺言の通りに実行されるとは限らないという点に注意が必要です。
また、記載内容は明確にしておく必要があります。
たとえば、「後のことは長男に任せる」といった記載は、記載内容が抽象的過ぎるため、遺言書の解釈を巡って争いが生じる可能性があります。
「兄弟で平等に分ける」といった記載も、どのように分けるのが平等なのか基準が明確になっていないため、トラブルになる恐れがあります。
無用な争いを避けるため、どの財産を誰に渡すかなどについては明確に記載しておく必要があります。
自筆証書遺言の保管方法で注意点はありますか?
遺言書の保管については何らかの対策をしておかないと、せっかく作成した遺言書が無意味なものになる可能性があります。
遺言書は、相続発生後、誰かの手によって実現されなければ意味がありません。
たとえば、誰にも遺言書があることを伝えなかった場合、相続人が遺言書の存在を知らないまま遺産の分け方を決めてしまう可能性があります。
また、家の掃除をしている時に間違って捨ててしまうような可能性もあります。
このようなリスクを回避するため、例えば、法務局の自筆証書遺言保管制度を用いるといった対策が考えられます。
これにより、紛失をさけられますし、勝手に書き換えられてしまう心配もなくなります。
参考リンク:横浜地方法務局・自筆証書遺言保管制度について
自筆証書遺言の保管方法について、詳しくは、専門家に相談することをおすすめします。
夫婦で自筆証書遺言を作成しようと思っていますが連名で共同の遺言書を作成しても大丈夫ですか?
連名の遺言書は無効になります。
法律上、自筆証書遺言は、2名以上が共同で作成することはできません。
夫婦で遺言書を作成する場合、必ず別々の用紙に、独立した内容を記載してください。
認知症でも自筆証書遺言の作成はできますか?
認知症の程度によって、自筆証書遺言の作成ができるかどうかが異なります。
たとえば遺産の分け方を指定する場合は、誰に、どの財産を取得させるかを遺言書に記載する必要があります。
そのため、自分がどのような遺産を持っていて、それを誰に渡したいのかということを最低限認識できていないと、遺言書の作成は困難です。
また、法的に有効な遺言書を作成できたとしても、「認知症が疑われる状態で作られた遺言は無効なのではないか」という疑問を抱く相続人が現れ、トラブルに発展してしまうケースも考えられます。
遺言書の作成は、可能な限りお早目に取り組まれることをおすすめいたします。
遺言の作成はどのような流れで行うのですか? 遺言の有効・無効についてのQ&A