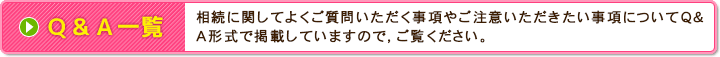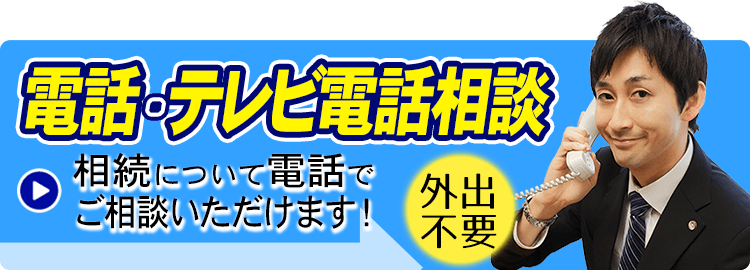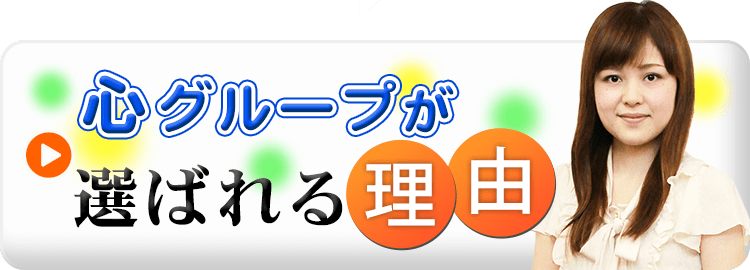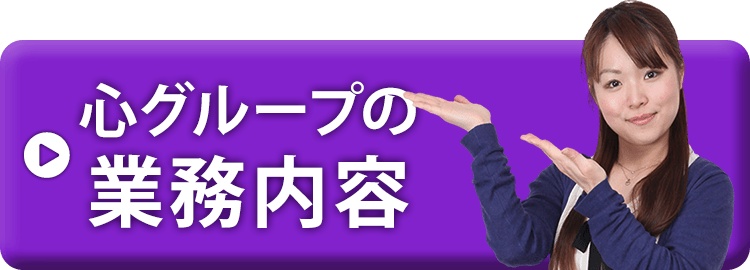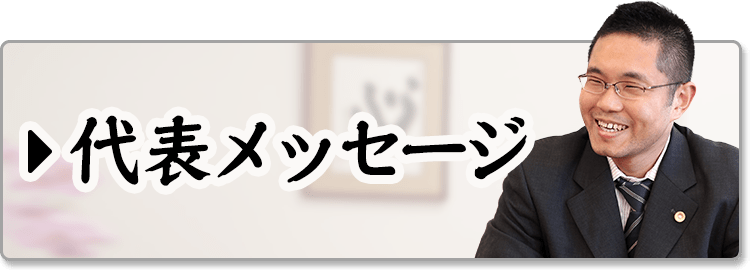相続で相続放棄・遺留分放棄の念書に効力はあるのか
1 相続放棄・遺留分放棄の念書は有効な場合と無効な場合がある
結論から申し上げますと、相続放棄や遺留分放棄をする旨を記載した念書は、作成された時期や相手によって、有効である場合と、そうでない場合とがあります。
念書が無効となる場合、後になってトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
以下、相続開始前と相続開始後に分けて、作成された念書の効力について説明します。
2 相続開始前に作成された相続放棄・遺留分放棄の念書の効力
⑴ 相続放棄の念書について
相続放棄は、相続が開始される前(被相続人がお亡くなりになる前)にすることはできません。
そのため、相続開始前に相続放棄をする旨の念書を他の推定相続人等に差し入れたとしても効力はなく、念書を差し入れた相続人は相続開始後に相続権を主張することができます。
⑵ 遺留分放棄の念書について
遺留分の放棄をする旨の念書を相続開始前に作成し、遺言者や他の推定相続人、受遺者に差し入れたとしても、効果はありません。
遺留分は相続開始前であっても、家庭裁判所で手続きをし、許可を得ることにより放棄することができます。
もっとも、家庭裁判所に申立てをすれば必ず放棄できるというものではなく、法律で保障された最低限の取り分である遺留分を受け取る権利が失われても本人に不当な不利益がないといえるだけの合理的な事情(すでに十分な生前贈与を受けているなど)がないと、許可はされないものと考えられます。
3 相続開始後に作成された相続放棄・遺留分放棄の念書の効力
⑴ 相続放棄の念書について
相続開始後に相続放棄をする旨の念書を作成し、他の相続人に差し入れた場合、相続人間では有効となり、相続財産を取得しないことになります。
一方、相続人以外の第三者に対しては、相続放棄の念書は効果がないため、被相続人の借金などの相続債務は負担することになります。
⑵ 遺留分放棄の念書について
遺留分の放棄をする旨の念書も、相続開始後に作成したものであれば基本的に有効となります。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知った時から1年間が経過すると時効により消滅します。