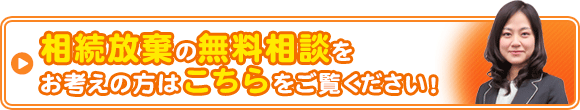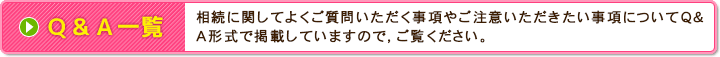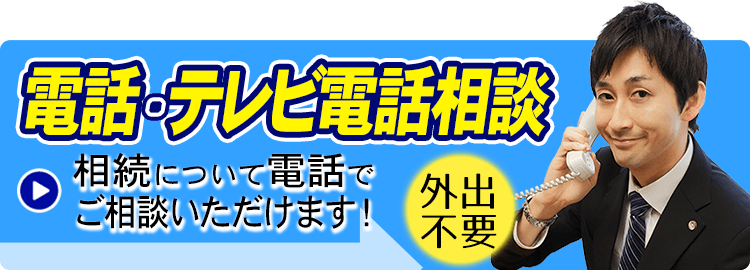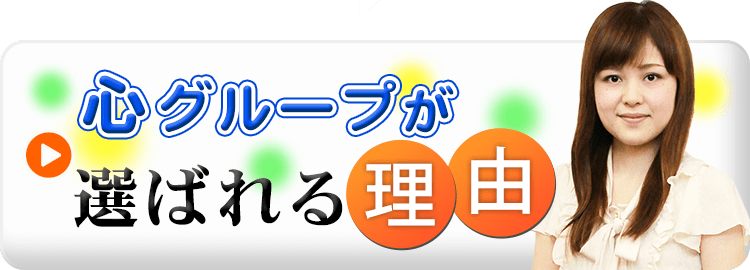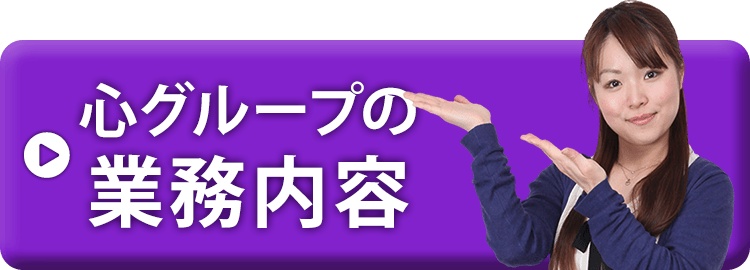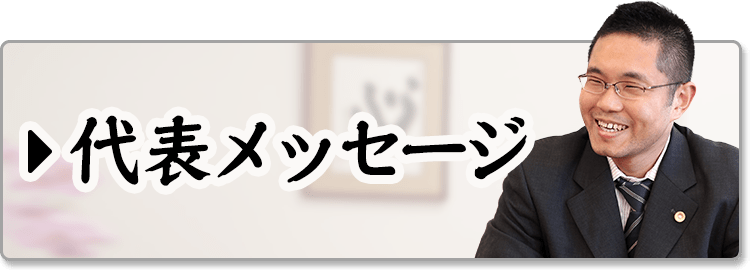生活保護を受けていた人が亡くなった場合の相続放棄
1 財産が残っていないことが多い
生活保護を受けるには、収入が最低生活費以下であること、保有資産が一定以下であることなどの条件があります。
そのため、生活保護を受けていた方が亡くなった時点で、プラスの財産が残っている可能性は低いです。
相続をしても、遺産がマイナスになってしまうことが多いため、相続放棄をした方がいいケースが多いといえます。
2 死亡から数か月以上経ってから請求が来ることがある
「借金がないから相続放棄しなくても大丈夫だろう」と放っておくと、長期間が経過してから、突然債権者を名乗る者より金銭を支払うよう請求をされてしまうということもあります。
生活保護を受けている人が、実は消費者金融などからの借金の返済を滞納していたということもあります。
そして、一般的には、生活保護を受けていた方が亡くなってすぐに相続人に請求が来ることはあまりありません。
独り暮らしの方が亡くなった場合には、発見後、消費者金融等が相続人や、その相続人の住所を調査し、その後に請求書を送ってきます。
相続人の住所等の調査には時間がかかるため、生活保護を受けていた方が亡くなった半年後や1年後などに、相続人に請求書が届くということもあります。
相続放棄は、亡くなったことを知った日から3か月以内に行う必要があるため、請求書が届いてから相続放棄をしても認められないことがあります。
そのため、相続人に借金等の返済請求が来ていなくとも、相続放棄をしておくことをおすすめします。
3 生活保護費の返還を求められることも
生活保護を受けていた方の場合、相続人が、数百万円の生活保護費の返還を求められることがあります。
例えば、「本当は資産を持っていたものの、緊急的な措置で生活保護費を受給した場合」や、「虚偽の申告をするなどして、不正に生活保護費を受給した場合」などは、生活保護費の返還義務を負います。
仮に亡くなった方が生活保護費の返還義務を負った状態で亡くなった場合、相続人がこの義務を相続することになります。
生活保護費の返還を避けるためには、相続放棄をする必要があります。
相続放棄の手続きの期間 相続放棄をする場合に遺品整理をしてはいけないのか