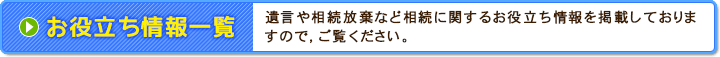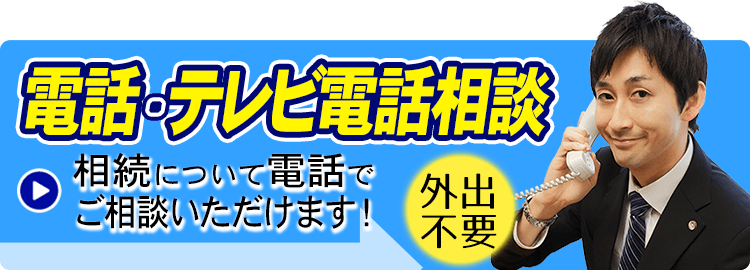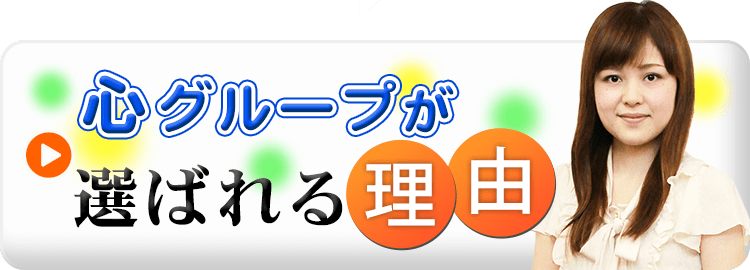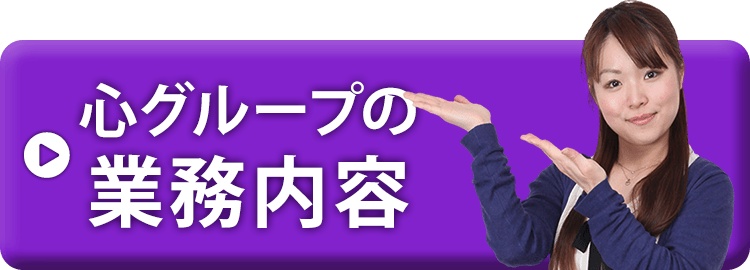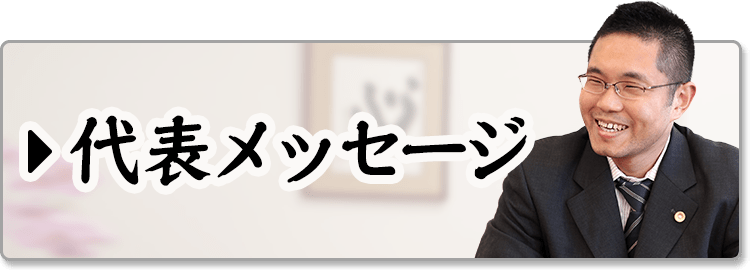寄与分についてのQ&A
寄与分に時効はありますか?
遺産分割協議では、寄与分は何年前のものでも主張をすることができます。
もっとも、特別寄与料の支払請求は、相続の開始と相続人を知ったときから6か月以内でないと、家庭裁判所への申立てができないため、注意が必要です。
参考リンク:裁判所・特別の寄与に関する処分調停
寄与分は相続人以外でも認められますか?
寄与分は、原則的に相続人のものしか認められません。
しかし、状況によっては、相続人以外の人に対しても寄与分が認められる場合があります。
例えば、妻が亡くなった義理の母親の介護をしていたケースで、妻の介護は、相続人である夫による介護をサポートしたものとして、寄与分にあたるとした裁判例があります。
寄与分は相続法改正で何が変わりましたか?
相続法改正で、特別寄与料の制度が創設されました。
今までは、寄与分の主張は相続人でなければできませんでした。
そのため、例えば亡くなった方の子供達は自立し、親の介護は親の兄弟がしていたケースなどでは、その兄弟は寄与分の主張はできませんでした。
しかし、特別寄与料は、親族であれば相続人でなくとも支払い請求ができます。
先程のケースでは、亡くなった方の兄弟は、亡くなった方の子供達に寄与料の支払いを求めることができるようになりました。
寄与分と遺留分侵害額請求との関係はどうなりますか?
寄与分に対しては、遺留分侵害額請求はできません。
以下に、例を挙げます。
例)親Aが亡くなり、その子供B・C・Dが相続したケースで、遺産総額が3000万円あり、Bに寄与分が2100万円認められた場合
寄与分2100万円を除いた900万円(3000万円―2100万円)を、子供3人で分けることになります。
そのため、それぞれの相続分は以下のようになります。
B:2400万円(=900万円÷3+寄与分2100万円)
C:300万円(=900万円÷3)
D:300万円(=900万円÷3)
このとき、C・Dはそれぞれ500万円(=3000万円×1/2×1/3)の遺留分を有しているため、遺留分を侵害されていることになります。
しかし、Bが受け取った2100万円が遺留分を侵害するとして、C・DはBに対し200万円を請求することはできません。
これは、遺留分侵害額請求の対象となるのが遺贈と贈与に限られ、寄与分は対象とできないからです(民法1031条)。
そのため、寄与分によりC・Dの取得額が遺留分を下回ったこのケースでは、遺留分侵害額請求はできません。
寄与分はどのように計算すればいいですか?
寄与分の計算は、寄与行為の内容によって異なります。
例えば、家業を手伝っていた場合は、本来得られたであろう給与額を考慮したり、介護をしていた場合は、介護サービスにかかるはずだった費用を考慮するなど、様々な要素があるため、寄与分の計算は複雑です。
相続と空き家に関するQ&A 相続にあたって家族と縁を切る場合のQ&A