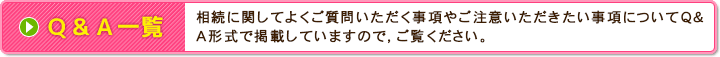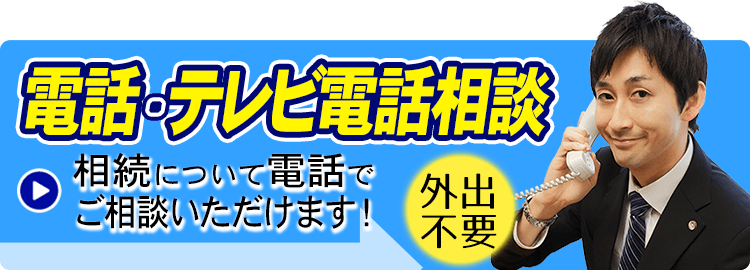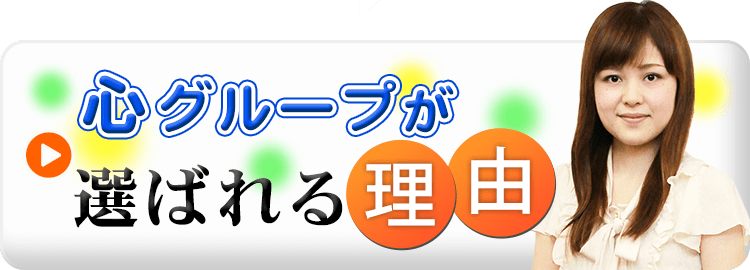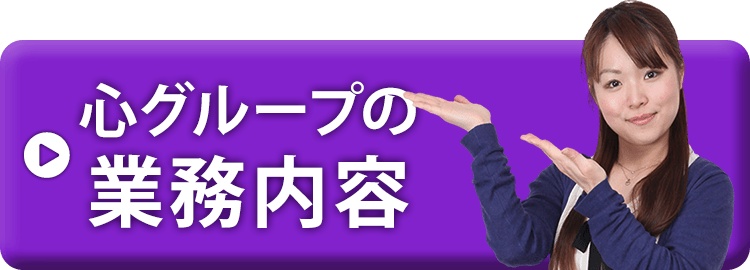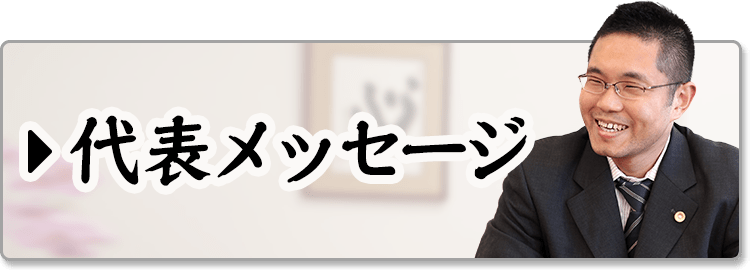相続預金の払戻しについて
1 遺産分割前の相続預金の払戻し制度の概要
被相続人がお亡くなりになって相続が発生すると、金融機関の預金口座は凍結され、原則として遺産分割協議が成立するまでは、相続人による払戻しはできなくなります。
遺産分割協議が調うまでは長い時間を要することもありますので、急な葬儀費用や生活費等が必要になった場合、対応が難しくなるという問題があります。
このような背景から、2019年7月の民法改正により、遺産分割前の預金の払戻し制度が創設され、一定の範囲内であれば、遺産分割の手続きを経ることなく、相続人が単独で被相続人名義の預金を引き出すことが可能になりました。
2 払戻しで引き出せる金額
遺産分割前の預金の払戻し制度を利用して払戻しができる金額には、上限が定められています。
具体的には、次のいずれか少ない方の金額が上限となります。
①相続開始時の預金残高 × 法定相続分 × 1/3
②金融機関ごとの上限額として150万円
例えば、被相続人の口座に900万円の預金があり、相続人が子2人(法定相続分はそれぞれ1/2)の場合は、900万円 × 1/2 × 1/3 = 150万円が上限となります。
手続きにおいては、一般的には、本人確認書類や相続関係を証明する戸籍謄本類などが必要となります。
3 相続預金の払戻しにより引き出した被相続人名義の預金の扱い
この制度により相続人が単独で払戻しを受けた金銭は、あくまでも遺産分割協議前の、相続財産の前渡しとして扱われます。
つまり、遺産分割協議の対象から外れるわけではなく、後の遺産分割の際には、その分を考慮して相続財産の分け方を調整する必要があります。
例えば、相続人のひとりが遺産分割前に100万円を引き出していた場合、その金額は相続財産の中からすでに取得したものとして取り扱い、最終的に相続財産の配分をする際に清算するという方法が考えられます。
このため、払戻しを受けた金額については、相続人間でのトラブルを避けるためにも、いつ、誰が、いくら引き出したのかを記録し、他の相続人に対して客観的な資料を用いて説明できるようにしておくことをおすすめします。
相続で相続放棄・遺留分放棄の念書に効力はあるのか 神奈川区にお住まいで相続についてお悩みの方へ