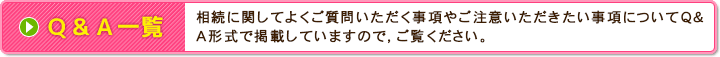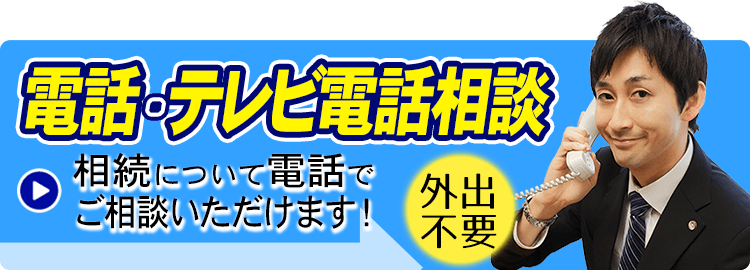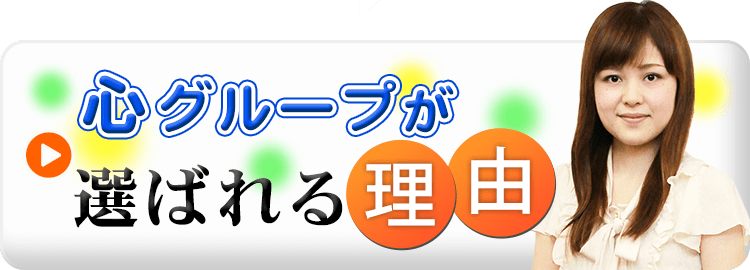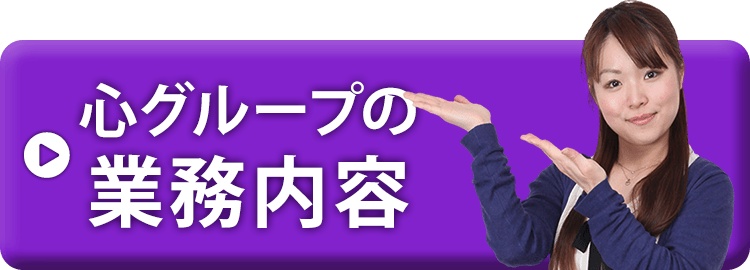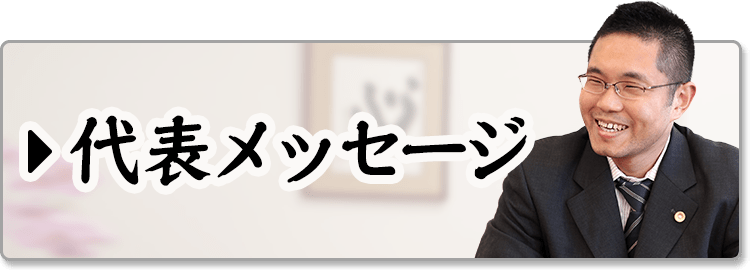生前贈与の失敗事例
1 生前贈与の目的
生前贈与は、相続税を合理的に軽減する手段として有効活用することができます。
相続税は、基本的には、相続時点で被相続人が有している財産について課税されます。
裏返せば、相続時点で被相続人が有している財産を合理的に減少させることができれば、相続税が軽減される可能性があります。
生前贈与を利用すれば、被相続人が相続時点で有している財産を減少させることができますので、相続税を軽減することに繋がります。
このような理由から、生前贈与は相続税対策として有効活用することができます。
もっとも、生前贈与による対策も、進め方次第では、まったく無意味に終わってしまうことがあります。
ここでは、生前贈与の失敗例を紹介し、生前贈与で注意すべき点をご説明したいと思います。
2 生前贈与したものと扱われなかった場合(預貯金)
生前贈与の方法として、子や孫名義で預貯金をするという方法が用いられることがあります。
確かに、自身の預貯金の名義を子や孫のものに変えてしまえば、贈与がなされたものと扱われると思いがちです。
しかし、実際には、預貯金を子や孫の名義に変えただけでは、贈与がなされたものと扱われないことがあります。
この点は、税務調査でも多々指摘がなされる部分です。
問題になりやすいのは、名義変更された預貯金について子や孫が通帳や証書を管理していない場合や、銀行印がご自身のものと同一のものになっていた場合、子や孫自身が出金して使うことがないような場合です。
このような場合には、預貯金が贈与された実態がないものと扱われ、いわゆる名義預金として、相続発生時に、相続税の課税対象とされるおそれがあります。
このため、相続対策で贈与を行ったと思っていても、相変わらず相続財産として扱われることとなってしまい、まったくの失敗に終わってしまうこととなります。
3 生前贈与したものと扱われなかった場合(生命保険)
生命保険が、贈与による相続税対策の手段として利用されることがあります。
具体的には、子や孫の名義で生命保険の契約を行い、保険料の引落はご自身の口座から行うという方法です。
このようにして、引き落とされる保険料を年間110万円以下にしておけば、保険料を贈与税が課税されない範囲で贈与したこととなる一方、将来に被保険者が亡くなった場合には、多額の保険金が子や孫に支払われることとなるといった説明がなされることとなります。
確かに、このような方法で贈与を行うという相続税対策もあるにはありますが、実のところ、この対策を有効に成立させるためには、いくつかの条件を整えるべきです。
国税庁は、保険料の引落が被相続人の口座からなされていた場合について、贈与契約書の作成や贈与税の申告、子や孫の側での確定申告時の生命保険料控除の利用がなされているときは、保険料が贈与されたものと扱うものとしています。
一方そうでない場合は、贈与されたものと扱わない可能性があるとしています。
このため、保険料の贈与という対策を用いたい場合は、贈与契約書の作成や贈与税の申告、子や孫の側での確定申告時の生命保険料控除の利用といった手立てを打っておいたほうが安全であることとなります。
反対に、このような手立てを打っていなければ、保険料の贈与がなされたものとは扱われず、いわゆる名義保険とされ、相続発生時に相続税の課税対象とされるおそれがあることとなります。