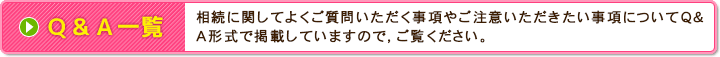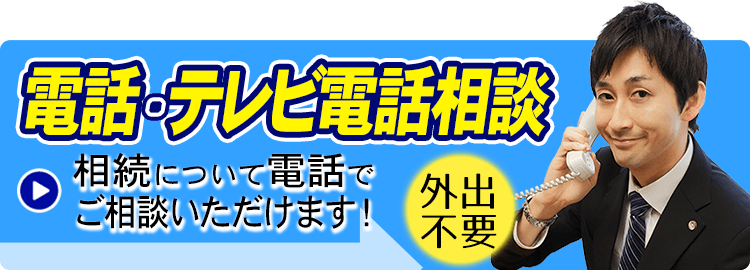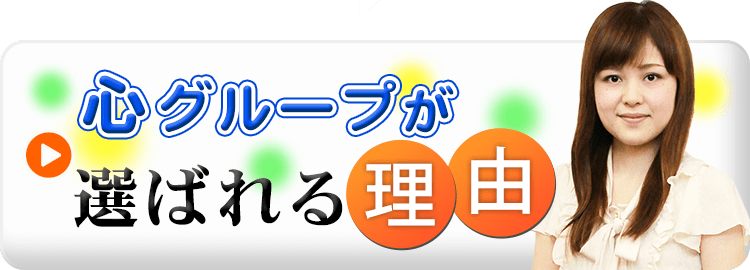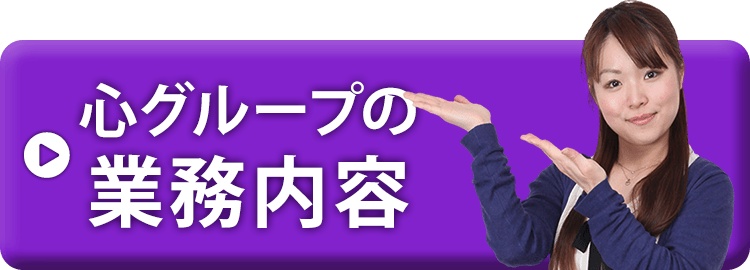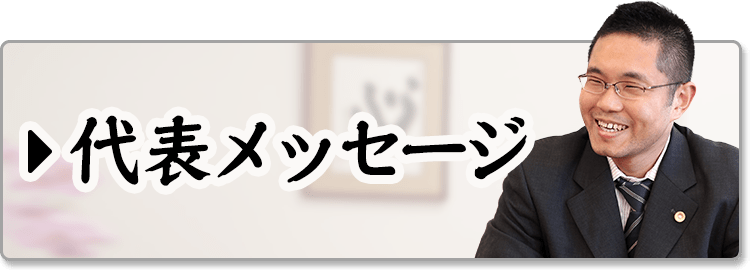寄与分の計算方法
1 計算方法は寄与行為の種類により異なる
「寄与分」といっても、亡くなった方のために行った貢献行為には様々な形があります。
寄与分では、その行為をしたことで亡くなった方の財産がどれだけ増えているかが重要となります。
そのため、貢献行為の種類によって、その計算方法が変わります。
例えば、親の介護をしていた場合は、それによって介護サービスや老人ホームを利用しないで済んだことにより、サービス利用料を支払わなかった日数分の財産が増加しています。
一方で、親のために家を購入した場合は、増加した財産は家そのものになります。
このように、貢献行為の形によって、寄与分の計算方法はまったく異なってくるのです。
以下では、貢献行為ごとの計算方法について例をご紹介します。
2 家業を手伝った場合(家業従事型)
例えば、実家が農家を家業としており、相続人が家業を共に支えてきた場合を考えてみましょう。
このような場合の計算方法は、次の2種類あります。
① 相続人が通常得られたであろう給付額×(1-生活費控除割合)×寄与期間
② 相続財産の総額×相続人が相続財産の形成に貢献した割合
①は、相続人が家業ではなく正式に雇われてその仕事をしていた場合に得られたはずの給料を計算する方法です。
家業に従事している場合は、被相続人と相続人が同居し、家賃や生活費も全て被相続人が負担している場合が多いため、その割合を「生活費控除割合」として減額しています。
②は、例えば、30年近くの長期間、父親と長男で一緒に農業を切り盛りしてきたという場合に用いられる計算方法です。
この場合は、家業に対する貢献の割合を、父70%、長男30%というように計算して、遺産のうち30%を寄与分として認めることになります。
3 被相続人に金銭等を贈与した場合(金銭出資型)
次に、親のために家を購入した場合や、夫婦で半分ずつ出資して購入した不動産をどちらかの単独名義にする場合の寄与分についてです。
この場合の計算方法は
- ① 不動産等の贈与の場合
-
相続開始時の価額×裁量割合
- ② 不動産の使用貸借の場合
-
相続開始時の賃料相当額×使用期間×裁量割合
- ③ 金銭の贈与の場合
-
贈与金額×貨幣価値変動比率×裁量割合
- ④ 金銭の融資の場合
-
利息相当額×裁量割合
などがあります。
基本的には、出資したものを亡くなった時の価値に評価した金額が、そのまま寄与分になります。
4 介護をした場合(療養看護型)
被相続人が、病気や高齢により独りで生活できなくなっており、子どもがその世話をしていた場合についても考えてみます。
このようなケースは、相続人の介護がなければ介護サービスや老人ホームの費用が必要になるところですが、介護によってその支払いをせずに済んだということで、寄与分として認められることがあります。
計算方法としては、
看護行為報酬額×日数×裁量割合
となります。