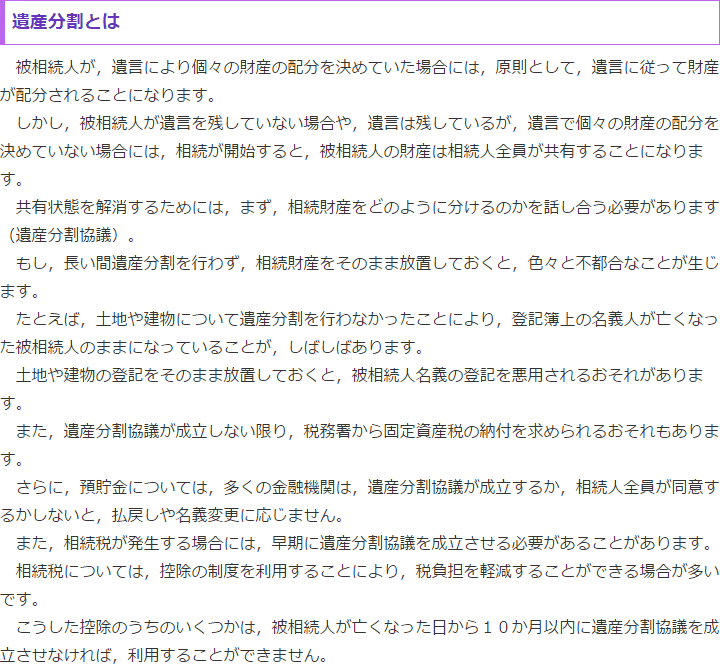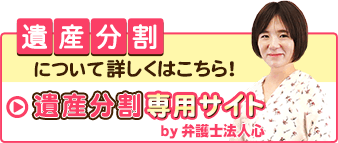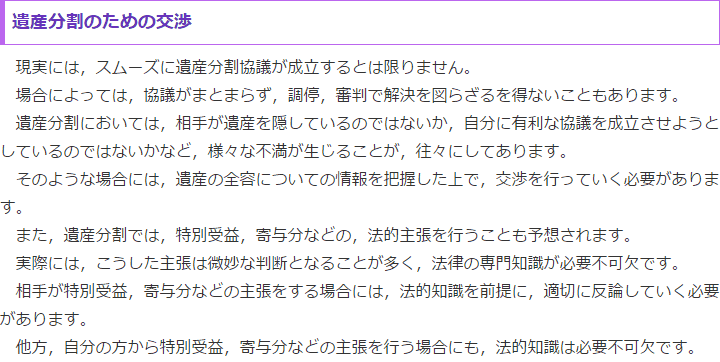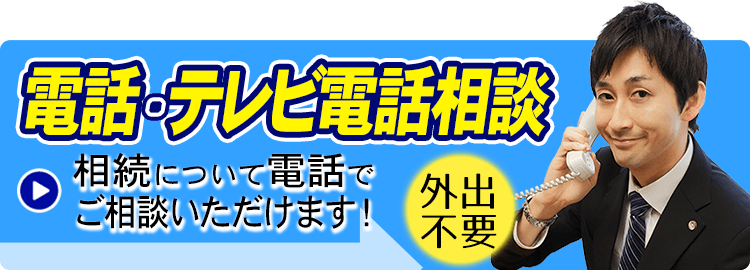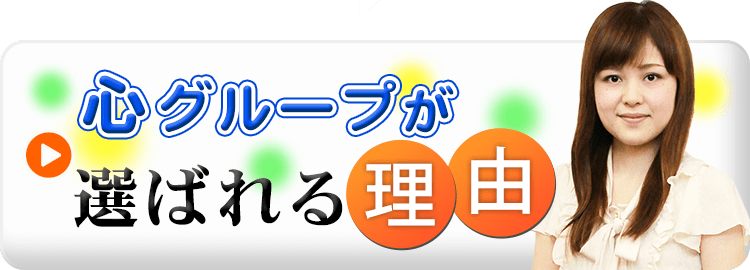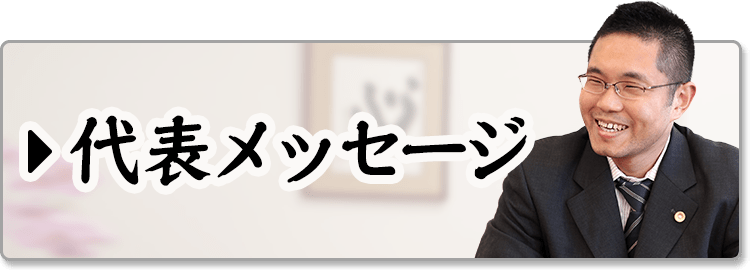遺産分割
遺産分割の流れ
1 遺産分割の流れについて

遺産分割は相続人全員で遺産の分割方法を決定すれば足りるので、これから記載する全ての段取りを踏む必要がないケースもありますが、分からなくなった場合には以下の記載を参考にしてください。
⑴ 相続人の確定
遺産分割協議は、原則相続人全員で行います。
そのため、最初に戸籍を確認し、「相続人の確定」を行うことが必要です。
具体的には、親子相続であれば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人が現在在籍している戸籍を取得することになります。
兄弟相続等の場合には、上記に加えて被相続人の親が亡くなっていることを示す戸籍等が必要です。
また、相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなっており、その子らが相続する場合など(代襲相続)や、遺産分割協議の成立前に相続人が亡くなり、新たに相続が発生した場合など(数次相続)には、より取得する戸籍は増えます。
⑵ 遺産の範囲の確定と遺産の評価
次に、「遺産の範囲の確定」をします。
要するに分割すべき遺産の洗い出し作業です。
そして、「遺産の評価」について、合意をします。
不動産がある場合で、特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人がお金で受け取る場合等には、不動産の評価額を合意する必要があるからです。
⑶ 分割方法を決定
最後に「分割方法を決定」します。
分割の方法や各相続人の取得割合は自由ですが、法定相続分の取得を主張する相続人がいる場合には、原則として法定相続分で分割されます。
ただし、特別受益や寄与分等、遺産の前渡しや遺産の増加への貢献が考慮されるケースがあります。
これらすべてが決定したら、遺産分割協議書に合意内容を落とし込んでいき、相続人全員が署名及び実印による捺印を行って完了となります。
2 遺産分割についてご相談ください
遺産分割は、亡くなった方の財産を相続人全員でどのように分割するかを決定することで、主に、凍結される金融機関の口座の解約や不動産の名義変更手続のために遺産分割協議書を作成して、各種手続を行うのが目的となります。
遺産分割について疑問が生じたり、争いになってしまったりした場合にはお気軽にご相談ください。
相続の事件を集中的に取り扱う弁護士が対応しますし、相談料は原則無料で対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
遺産分割で揉めやすいケースと対応方法
1 遺産に不動産があるケース

親が亡くなり、子Aと子Bが相続人になりました。
遺産は、自宅と預金3000万円です。
このケースの場合、子A・Bの2人で遺産を2分の1ずつ分けようとすると、自宅をいくらと評価するかによって、分け方が大きく変わってきます。
自宅の評価を1000万円とすると、子Aが自宅と預金1000万円、子Bが預金2000万円を相続することになります。
しかし、自宅の評価を3000万円とすると、子Aが自宅のみを相続し、子Bが預金3000万円全額を相続することになります。
このように、自宅の評価によって、受け取る預金の金額が数百万円~数千万円単位で変わってしまうケースもあります。
不動産の評価には様々な評価方法があるうえ、評価をする人によって金額が変わりやすいため、揉めやすい部分です。
遺産に不動産があるケースの対策方法としては、早めの段階から専門家を入れて話し合いを行うことです。
ある相続人は不動産を時価(=売却したときの金額)で評価することを主張しているが、別の相続人は固定資産税評価額(時価の7割程度)や相続税評価額(時価の8割程度)で評価することを主張している場合などでは、話し合いの溝が深まるばかりです。
そのため、早めの段階で専門家を入れて評価方法を統一するなど、話し合いの土台を決めていくことが一つの対策となります。
2 生前贈与を受けた相続人がいる場合
親が亡くなり、子Aと子Bが相続人になりました。
遺産は、預金3000万円です。
子Aは、結婚して自宅を建設するときに、親から1000万円の贈与を受けています。
一部の相続人が生前贈与を受けた場合、特別受益として、相続の際の取り分が減ることがあります。
上のようなケースの場合、子Aは生前贈与1000万円と預金1000万円を受け取り、子Bは預金2000万円を受け取ります。
しかし、生前贈与がすべて特別受益として相続の取り分を減らすわけではありません。
特別受益は「遺産の前渡し」としての贈与である必要があり、親と同居して生活費をすべて支払ってもらっていた場合や、家業を継ぐために学費を支払ってもらっていた場合などは、特別受益になりません。
また、何年も前の場合は、証拠が残りにくいです。
そのため、「お金は貰ったが、生活支援のためだったから相続には関係ない」「証拠は無いが、あいつは多額の生前贈与を受けているはずだ」など、揉める火種となりやすい部分です。
対策方法としては、生前贈与をする際に、親に書面を作成してもらいサインと判子を貰うなどして、証拠をはっきり残しておくことが効果的です。
親に、持ち戻しの免除(=生前贈与を遺産分割に反映させないこと)することを書面で残してもらえれば、相続の際に生前贈与を追及されなくなります。
また、他の相続人が生前贈与を受け取っている場合、贈与契約書などを残してもらえば、相続のときに追及をしやすくなります。
3 親の面倒を見た相続人と面倒を見ていない相続人がいる場合
親が亡くなり、子Aと子Bが相続人になりました。
遺産は、預金3000万円です。
子Aは、親と同居し、親が認知症になった後も仕事を休みながら介護をしていました。
子供が親を介護した場合などには、親の相続の際に、寄与分としてその子供の取り分を増やす制度があります。
例えば、親が要介護5で老人ホームに入らなければ生活は困難であった場合に、子供が懸命に介護したおかげで老人ホームに入らず、2000万円の入所費用を支払わないですんだ場合は、2000万円が寄与分となります。
そうすると、分け合う遺産は、預金3000万円から寄与分2000万円を引いた1000万円ということになり、子Aと子Bはそれぞれ500万円ずつ遺産を相続することになり、それに加えて子Aは寄与分として2000万円を相続することになります。
しかし、介護は日常的に行うもので何年間もの期間をかけて行うことから、子Aがどれだけの介護をしたのか、その介護によりどれだけ出費を免れたのかなどがわからず、証拠が乏しいことがほとんどです。
そのため、対策方法としては、領収書や日記を細かく残すなど、介護したことの証拠をしっかり残すことが大切です。
また、親が介護が必要な状態であったことを証拠に残すため、診断書などを残しておくことも有効です。
4 揉める前に弁護士に相談を
遺産分割では、一度相続人同士が揉めてしまうと、解決の難易度は大きく上がってしまいます。
そのため、亡くなる前でも亡くなった後でも、揉めてしまう前に弁護士に相談をすることが大切です。
遺産分割協議書を作成するときの注意点
1 相続人全員の合意が必要

遺産分割協議は、相続人全員の合意があることが必要です。
相続人の一部が反対している場合や、相続人の一部が欠けている場合など、相続人全員の合意が確認できない遺産分割協議書は無効となりますので注意が必要です。
2 遺産分割協議書の記載
遺産分割協議書に預金等の金融資産を記載する場合、遺産を特定するために、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を正確に記載する必要があります。
また、不動産を記載する場合にも、登記簿記載に記載されている事項を正確に記載しなければなりません。
3 実印と印鑑証明書が必要
遺産分割協議書の押印は実印で行う必要があります。
また、実印で押したことを証明するために印鑑証明書も必要となります。
遺産分割協議書内容に則して預金等の遺産を分配する場合、各金融機関に預金の解約等の手続が必要となります。
遺産分割協議書に実印の押印が確認できない場合、各金融機関で手続を受け付けてもらえないので、この点は注意が必要です。
また、印鑑証明書の有効期間ですが、法務局で不動産の名義変更手続を行うだけなら、住所や氏名の記載が一致していれば、古いものでも手続を行うことができます。
一方で、金融機関や証券会社との関係では、有効期間が設定されていることがほとんどです。
有効期間は、多くの場合は発行から6か月ですが、短いところでは3か月とされています。