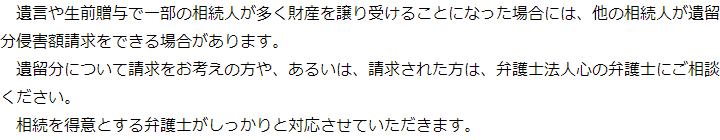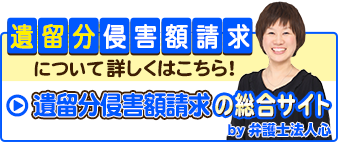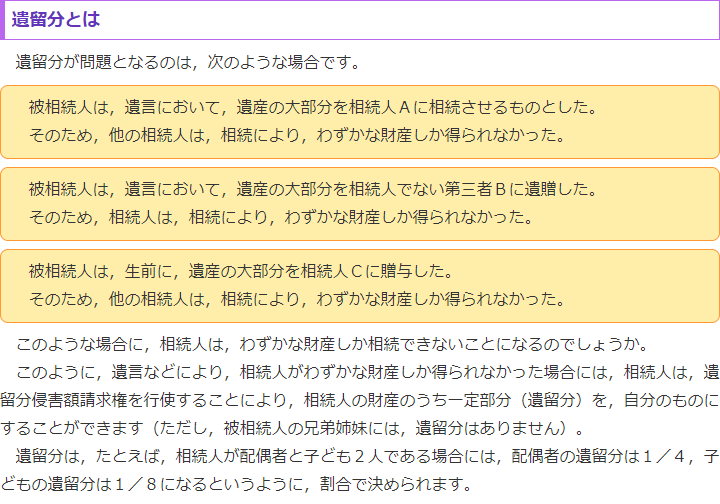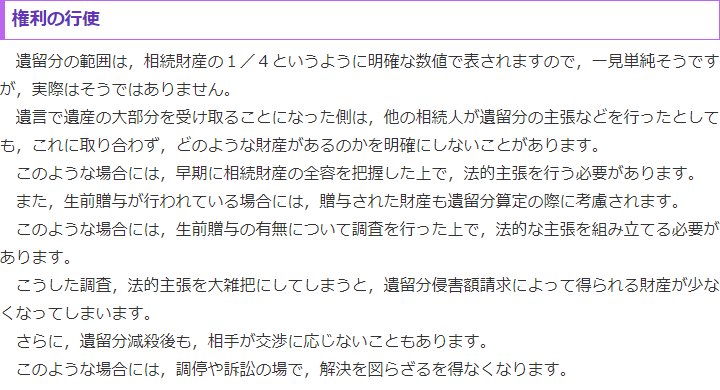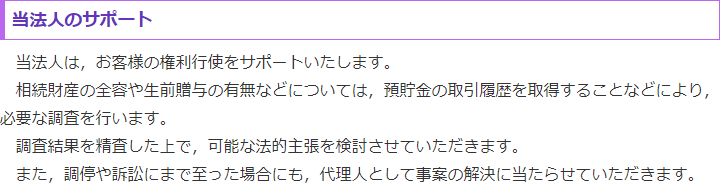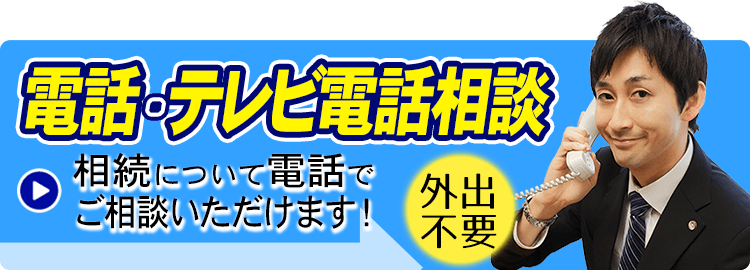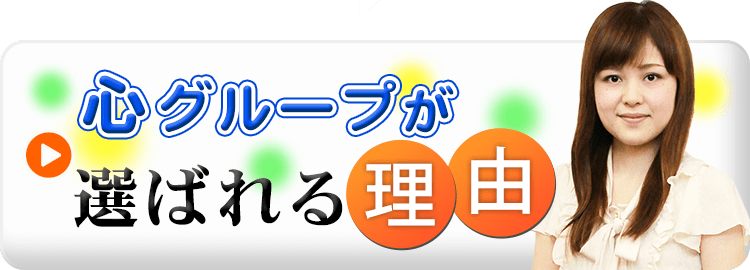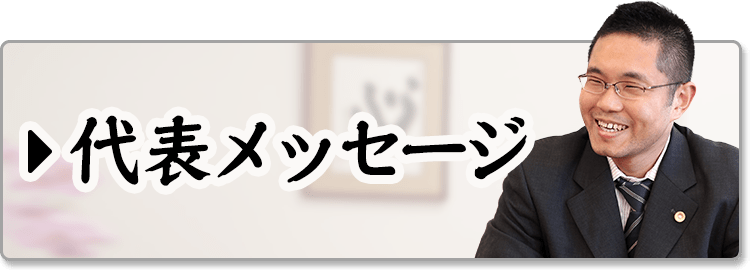遺留分侵害額請求
遺留分権利者の範囲
1 相続人でも遺留分を請求できない場合がある

遺留分について、相続人であれば誰でも請求ができるのかというと、そうではありません。
被相続人(亡くなった方)から見て、相続人が兄弟姉妹、甥姪の場合、遺留分を請求することはできません。
そのため、どんなに不利な内容の遺言書であっても、相続人が兄弟姉妹、もしくは甥姪の場合、有効な遺言がある限り、遺留分の請求はできません。
2 遺留分権利者の範囲
具体的に遺留分を請求することができる相続人のことを「遺留分権利者」といい、ここではその範囲についてご説明します。
遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属であり、子が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、子の子や孫(被相続人から見て孫やひ孫)も遺留分権利者に該当します。
相続人が子の場合、直系尊属(両親や祖父母)は、相続人ではありませんので、必然的に遺留分権利者ではありません。
なお、胎児は、無事に生きて生まれた場合は、子として遺留分権利者に該当します。
3 遺留分権利者に該当しない場合
遺留分権利者に該当しない場合として、相続欠格(遺言書を偽造した場合などが当たります。)、相続人廃除(被相続人に虐待を行った場合などが当たります。)、相続放棄によって相続権を失った人が挙げられ、これらに該当する場合は遺留分もありません。
ただし、相続欠格や相続人廃除の場合、相続権を失った相続人に子がいる場合、その子が遺留分権利者となります。
また、連れ子がいる人が被相続人と養子縁組をした場合、その養子が被相続人よりも先に亡くなった場合でも、連れ子は相続人ではないため、遺留分の権利はありません。
例えば、Aには子Bがおり、Aは被相続人Cと養子縁組をしました。
その後、Aが先に死亡した場合、Cの相続の際、BはCの相続人ではないため、遺留分の権利はありません。
このように、遺留分権利者に該当しない場合も様々ですので、ご自身が遺留分権利者に該当するかよくわからないという方は、一度、専門家にご相談ください。
私たちは、原則として、相談料無料で相続のご相談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。